
わたしはどうして、ごはんを食べようとしているんだろう?
中学三年生の多鶴は、とつぜん思い出した。
自分が、ロボットだということを。
もう、人間のふりをするのに疲れた。
今日を最後に、わたしは本当のわたしにもどろう。
そして多鶴は、もう「食べる」ということをやめる。
娘のことについてなんでも恋人に話してしまう母と、その同性の恋人。
三年間なにも良いことがなかったと、多鶴の前で学校を呪う友だち。
自分がロボットであるということを、唯一信じてくれる幼馴染の男子、まるちゃん。
彼らと生きる多鶴の世界には、さみしさと、息苦しさと、ほんの少しの救いがあった――
大人に変わろうとする心のありようをもてあまし、さみしさにあえぐひとりの少女。
彼女の目から見た、そのどうしようもなく息苦しい世界を、まざまざと描き出す衝撃作!
自分では正体のわからないさみしさに、もだえたことはありますか?
心はたしかに痛んでいるのに、それがなぜなのかわからない、そんなもどかしさに襲われたことは?
十代のころそういう苦しみのなかにあった、あるいは今まさしくそのさなかにあるすべての人に、やさしくよりそう一冊です。
なにも食べないせいで、どんどん衰弱していく多鶴。
そんな彼女を救うためにまるちゃんが差し出した手は、多鶴をどこに導くのか?
自分自身の心と向き合い、家族を、友だちを――そして、世界を見つめなおす物語。
(堀井拓馬 小説家)

わたしは、ロボットだった。
人間じゃなくて、ロボットだった。
そのことを、わたしはすっかり忘れて生きてきた。
きっと、忘れたまま生活するようにプログラミングされていたんだと思う。
だけど、思い出してしまった。
本当に突然、ふっと。(本文より)
自分がロボットであると認識し、食べることをやめた少女と
彼女を理解しようとする少年
ゆらぎ、見失いそうになる自分の形を
見つけるための物語
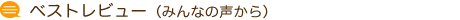
突拍子も無い事を言い出す少女が主人公。
自分がロボットだった事を思い出すって、なかなかないですよね。接触障害になってしまうんですけど、自分がロボットじゃないと思い込む事で自分を守っていた部分もあったのかな。
でも、彼女の家庭が変化していくことに対するショックは共感できる部分もあって、最後は彼女が前を向けている事にホッとしました。
(lunaさん 30代・ママ 男の子9歳)
|