|
|

詩の「つくり方」のヒントをちりばめたシリーズ。
2019年に萩原朔太郎賞を受賞するなど大活躍中の詩人、和合亮一さんを監修に迎え、
教科書に載っている有名な詩人の詩を引きながら、
「いろいろな詩を読んでみよう」、「身近なことを詩にしてみよう」と呼びかけます。
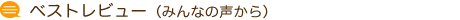
「詩は難しい」「特別な感性を持っている人の楽しむもの」(=自分には縁がない)と思い込んでいたが、本シリーズを見ると、自由に作品を味わって楽しんでよいとわかる。
自分の好きな作品をあつめてみよう、ということで、
事例が載っていた。
自分だったら、面白いもの、ギャグのようなもの、発想が突飛でビックリするもの、なぞなぞのようなもの…などを集めたいと思った。
詩は、格調高いものや、難解なもの、外国の作品だったり、時代が違うために意味を取りにくいものがあったりする。
しかし、漫画のように親しみやすいものや、一発ギャグのように愉快なものもある。
本書を見て、いろんな詩の世界があって、いろんなタイプの詩人がいることがわかり楽しかった。
詩は、自由な世界だとわかった。
(渡”邉恵’里’さん 40代・その他の方 )
|