
真夏の夜、元安川に、人々は色とりどりの灯籠を流す。光を揺らしながら、遠い海へと流れていく――。
68年前の8月6日。広島上空で原子爆弾が炸裂した。そこに暮らしていた人々は、人類が経験したことのない光、熱線、爆風、そして放射能にさらされた。ひとりひとりの人生。ひとりひとりの物語。そのすべてが、一瞬にして消えてしまった。
昨年、原爆をテーマに研ぎ澄まされた筆致で『八月の光』を世に問うた朽木祥が、今回、長編で原爆を描ききる。
日本児童文学者協会新人賞をはじめ、産経児童出版文化賞大賞など多数の賞に輝く朽木祥が、渾身の力で、祈りをこめて描く代表作!
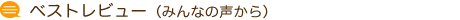
作者の朽木祥さんは1957年広島に生まれた、被爆二世の女性だ。
デビュー作『かはたれ』以降、児童文学で数々の受賞歴を持つ児童文学者で、広島の原爆を扱ったこの作品も児童文学に括られるでしょうが、成人が読んでも十分に鑑賞できるし、むしろどの世代であっても多くの感動が得られることと思う。
主人公は12歳になる中学生の希未。
終戦から25年とあるから、物語は昭和45年の広島だろう、おそらく主人公の年齢はほぼ作者と同じと思われる。
希未のまわりにはまだたくさんの戦争の犠牲者、原爆の被害者がいた。
美術部の顧問吉岡先生もその一人。あの日の原爆で許嫁であった女性を亡くしている。
身近な人にそんな悲しい出来事があったことさえ、あれから25年も経つと忘れていることに希未たちは愕然となって、身近な人たちの悲惨な体験を学ぼうと決める。
あの朝、ぐずる息子を叱り、追いやるように学校にせかした母の、悲しい後悔。
大きな骨の周りに寄り添う六つの小さな骨は、あの日原爆の犠牲にあった女先生とその先生を慕った学生たちではないか。
原爆だけではない。希未の母にも秘密があった。それはかつての恋人が遠い戦場で亡くなったこと。
愛する人を戦争で、原爆でなくなった、その事実を12歳の少女は知ることになる。
そして、そんな大切な人を忘れないということも。
この作品には「小山ひとみ」という戦争を詠んだ無名の歌人の歌が何度も出て来る。
朽木が書くように、世界にはたくさんの「小山ひとみ」がいるだろう。
それは何十年経っても忘れてはいけない。
(夏の雨さん 60代・パパ )
|