
庭にある鶏小屋にはにわとりがいて、毎朝卵を産みます。
起きたらすぐに、産みたてほやほやの卵をとりにくのがわたしの仕事です。
ある日のこと、鶏小屋にあひるがやってきました。
新しい生き物にわたしも弟も夢中になります。
川で一緒に遊んだり、はこべを食べさせたりしました。
次の日も、二人は下校すると真っ先にあひるのところへ向かいます。
でも、あひるはもういません。
わたしと弟の頭の中は、あひるのことでいっぱいです。
その日、台所でお母さんは美味しそうな野菜とお肉の煮物を作ってだしてくれました。お肉は、いつもの鶏肉とちがうかたさでした。
大人は、子どもの気持ちを察した返事をしてくれます。
でも、子どもは自分自身で気づいていくのでしょう。
色味を押さえた色彩が、よりいろいろな気持ちを連想させます。
毎日の食事に欠かせないお肉やお魚は、すべて命があるもの。わたしたちは生かされている。
そう気づくのは、現代の子どもたちには簡単なことではないのかもしれません。
でも、その事実を知ることは、その後の子どもたちに自分たちの「生きる」について考える豊かさを与えてくれるはずです。
作者の石川えりこさんご自身が子どもの頃に実際に体験した経験から作成された絵本です。
子どもと一緒に読んで、大人も考えたい一冊です。
(富田直美 絵本ナビ編集部)

食べるとは、命をいただくこと。
身近に経験する機会が少ない今、子どもたちに届けたい絵本です。
自宅の鶏小屋から、毎朝卵を取ってくるのが主人公「私」の日課です。
ある日、隣町のおじさんから、体が弱ったあひるが一羽届きます。私と弟は、初めて間近にみるあひるに興味津々。元気になってもらうために、翌日あひるを近所の川に連れて行くことにしました。
川で運動させると、あひるは食欲も出て、少し元気になった様子です。
あひるが元気になってうれしい二人は、次の日もとり小屋目指して、校門から駆け出します。ところがとり小屋につくと…
「あひるがおらん!」とり小屋にはにわとりしかいません。
台所に飛び込むと、そこはお醤油と砂糖のまじった、いい匂いでいっぱい。その日の夕飯は、私も弟も大好きな野菜とお肉の煮物でした。
大好きな煮物を目にして、私は何を思うでしょうか?
食事後に、「あれあひるじゃないよね」とお母さんに質問する弟を、私はどのような思いで見つめているでしょうか?
『あひる』は、生きることと食べることが身近にあった、著者の子ども時代を絵本化した作品です。ご家庭で、親と子が一緒に読んでもらいたいですし、また、学校や図書館での食育活動にもお奨めの一冊です。
読み終わったあとに、食卓に並ぶ、肉・魚を見て、子どもたちが何かを感じとってくれることを願っています。
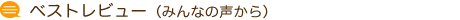
石川えりこさんの絵本に魅かれるのは、その作品に自分が育ったものと同じ匂いや光を感じるせいだ。
昭和30年(1955年)生まれの石川さんだから、その匂いや光は昭和のそれといっていいかもしれないが、ちがった言い方をすれば幼い時に見た風景がそこにあるからだともいえる。
この『あひる』という作品に描かれている日常もそうだ。
そこに描かれているのは、飼っているにわとりが生んだ卵を食べ、年をとったにわとりは「しめて」鶏肉というごちそうになる、そんな日常だ。
おそらく現代の子供たちは鶏肉は食べてことがあっても、「しめて」という行為は知らない。
石川さんも私も、「しめて」鶏肉を食べた世代だ。
ある日、姉と弟のきょうだいの家に一羽のあひるがやってくる。
家の前の川であひるを、お父さんのつくってくれた木の船(この船の絵が昭和生まれにはたまらなく懐かしい)と泳がせたたりしていた。
ところが、そのあひるがいなくなった日、きょうだいの家の夕ご飯は野菜とお肉がいっぱいの豪華な鍋でした。
姉は、もしやと気づきます。
弟も心配になって、お母さんに「あひるの肉じゃないよね」とたずねます。
お母さんは違うと答えてくれたけれど、姉はもうわかっています。
自分の周りの現実を知る年齢になっていたのでしょう。
にわとりを「しめて」鶏肉として食べることは残酷でしょうか。
石川さんや私が小さかった頃、そうやって「いのち」を感じとっていったのです。
(夏の雨さん 60代・パパ )
|