
『泣いた赤おに』や『むく鳥のゆめ』『りゅうの目のなみだ』など、数々の名作童話を生み出した浜田廣介さんの知られざる名作がこのたび絵本に。ページを開く前からどんなお話なのかワクワク感が募ります。
主役として登場するのは、ある町はずれに立っている一本のがい灯です。がい灯はもう年をとってよぼよぼでしたが、長い間「ひとつのねがい」を持ち続けていました。それは、「一生に、たった一度だけでいい、星のようなあかりぐらいになってみたい」という強い思い。ああ、だれかひとことぐらいは、おれをじっと見て、こいつは、まるで星みたい…と言ってくれたらなあ…。
しかし、秋も終わりに近づくと、がい灯のランプの光は、いよいよさびしくみすぼらしくなっていきます。さびしい小路の角でがい灯が出会うのは、こがねむしや白い蛾などちっぽけなものだけ。しかもちっぽけな虫の目にさえ全く星のようには見えないと言われたがい灯は、一気にどん底に突き落とされるのです。その失望の中で、がい灯の心に静かに湧きあがってきた思いと、光の輝きの変化とは…?
読み終わった後、しばらくお話から抜けられず、余韻が残る中で考えてしまいました。「自分のつとめを一心にとげようとする強さ」と「ねがいを持ち続けることの尊さ」を静かに読む者に訴えながら、「幸福」というものがどこからくるのか語りかけてくるようです。
「一つの願い」は1919年に作られたお話だそうですが、しまだ・しほさんのさし絵がその時代の情景を味わい深く醸し出していて、さらにお話の世界をぐっと引き立てています。2013年は廣介生誕120年を迎える節目の年だそう。この機会に、初めて絵本になった廣介童話の一作にぜひ触れてみませんか。
(秋山朋恵 絵本ナビ編集部)

いつもだまって道を照らしている街灯。その街灯は、長い間ひとつの願いを持ちつづけていました。──一度は星のように輝きたい──そんな大それた願いを抱く街灯が、自分のつとめに無心に専念したとき、思いがけない幸福が訪れるのです……。「幸福」はどこから来るのか、探してみませんか?おはなしは、「泣いた赤おに」で知られる浜田廣介が20代に書いた、知られざる名作です。しまだ・しほのこまやかでセンスのある絵によって、作品に新たな息吹が吹き込まれました。
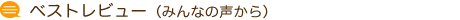
2年前に大病を患い、今は通院治療になったものの体調も以前とはまるっきり変わってしまった私にとって、外灯の存在が自分とリンクしてしまって、胸にこみあげるものがありました。
人は誰しも体の衰えを感じたり、命の期限をなんとなく見てしまったとき、まだ何かこの世に残したい、やり残したことはないかと考えるものではないでしょうか。
外套の願いをかなえたいという外灯の想い、無理しなくても細々と生きていくのではなく、今できることを精いっぱい生きようという気持ちに
今の私だからこそ共感できたのではないかと思います。
最後に願いが叶ったことは、外套にとって幸せですよね。
温かい言葉をかけてくれた少年だけでなく、相手にしなかった虫たちの存在も、すべてが外套の最期の力を振り絞る源となってるのだと思います。
私は外套からエールを送られたような気がしました。私の余生のバイブルとして繰り返し読みたい一冊です。
(きゃべつさん 40代・ママ 男の子16歳、男の子13歳)
|